みなさん、こんにちは。
『リタイア生活 in ラスベガス』ブログのマーゴです。
今この時もご家族の在宅介護に従事されているシニアの皆様、毎日お疲れ様です。
家族の介護は肉体的精神的に重労働のルーティーンの毎日!一日でも欠かせばあなたのご家族(被介護者)の命にかかわるので休むことは到底不可能です。
私はいつも悩み苦しんでいました。
「これ、いったいいつまで続くの?」と。
終わりのない暗闇のトンネルのように永遠に続く介護苦から逃れたい!
本ブログ介護シリーズの最初の記事、
『リタイア生活:介護からの脱出を戦略的に叶える!』!)の介護中の大きな悩み-その2,
今回は〔365日途切れない介護!休みがほしい〕編。
できることなら介護を終わってしまいたい!!
まさにそのアンサーは
介護の終わりを戦略的に決めてしまう! なのです。
少し手荒なのは承知ですが、この介護の苦しみを終わらせる期限を決め、計画を立てる ことによって
暗く長~いトンネルに一筋の光✨が見えてくるものです。不思議と。
思い切って「終わり」を決定し、自分で介護苦をコントロールする方法とコツを手に入れ
終わりのないの暗闇から希望の光✨✨が見えるように、プランニングしていきましょう。戦略的にです。😎
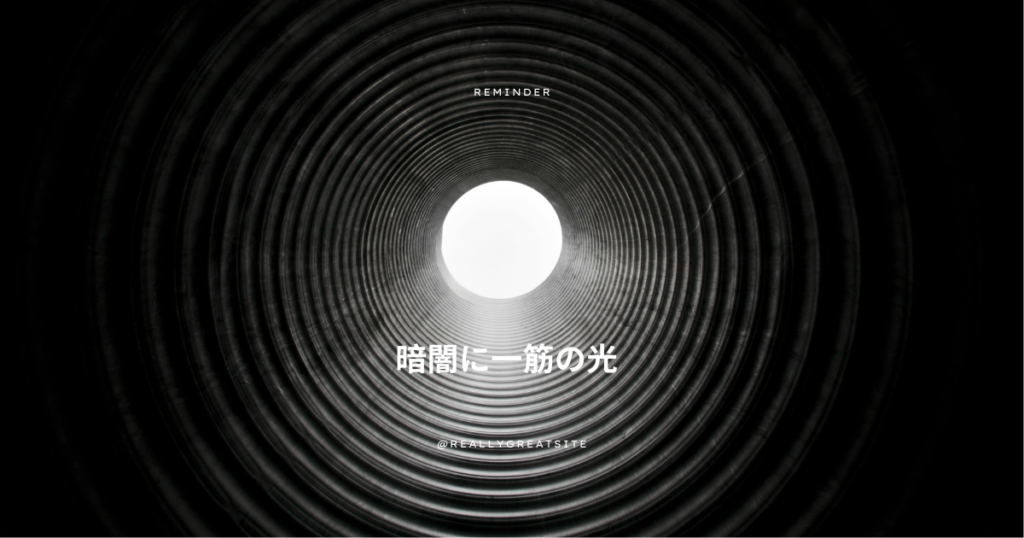
介護を終わりたい!を戦略的に決めてしまう
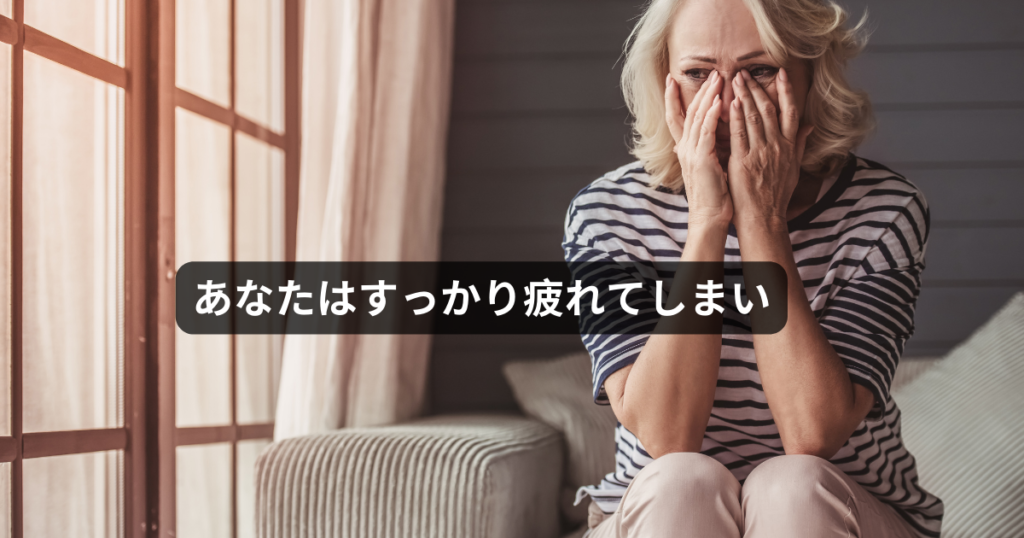
介護の終わりとは、ざっくり言って
①病気から回復してくれる時期
②介護を終了する時期
③生命の終わりを迎える時
だと思うのです。
それを決めてしまうのです。
それぞれ病人の病気の程度によると思うのですが、もちろん病人家族には元の元気な状態、せめて介護が要らないくらいまでに回復してほしいものです。
もちろんこの冷たい私、マーゴでさえそうでした。早く治って職場復帰してもらい(ウチの夫は職場が大好きだったので。)いつものなんでもないありきたりの生活に戻りたかったのです。
夫が急病で倒れた当時、私達はラスベガスのカジノホテルでフルタイムの仕事をしていました。二人とも夜のシフト勤務で、その夜夫は無事帰宅してくれたのですが、翌日彼は午前中に主治医クリニックで定期健診の予約があり、一緒に私も付き添いました。健診後、一緒に外食ランチに行く予定だったからです。
が、診察室で倒れ、即救急病院へ搬送で急きょ手術。原因はStroke(脳卒中)でした。夫65歳。
脳卒中から併発して、腎臓病発症と日頃の日頃の軽度の糖尿病がさらに悪化し、左半身不随の寝たきり状態、言語障害は免れたものの、腎臓人工透析を受ける状態になりました。
医者からは私だけにこう告げられました。
「年齢と病状から鑑みて、2年以内に50%の確率で脳卒中を引き起こす可能性があり、今度再発すると助かる見込みがない。」とのこと。
手術後の入院中、私は出勤前と出勤後にお見舞いに行ってました。せっせと。
そこで考えなければならないこと発生。
「再度脳卒中を起こさない為に、私は職場に看病休暇を取るべきだと。1か月か3か月取ろう! できるなら1年間。」
「じゃあいついつまでに○○をして、、、。」
「誰々に何を申請して、、、。」
「その間どう看病して、、、。」
などと普段、段取りを決めるのが苦手なのに、プランを立てました。
まず、1年後に回復する(今の8割でいいから)と仮定したのです。
つまり夫は1年後に治ると決めました。私だけのプランです。
計画倒れになってもいい。職場と家庭内でだいたいの青写真ができればそれでいい!
夫が退院したタイミングで例のコロナ禍発生。結局全ラスベガスじゅうのカジノは閉鎖になり、私はもちろん全従業員はリストラになりました。
そのおかげで看病休暇を取らなくてよくなった! 私が自宅で介護をすることになりました。
しばらくして、週に3回通院のしていた人工透析のクリニックから
「パンデミックの為、通院の人工透析は危険なので、奥さんが自宅でやってください。」
えぇぇ?? 私が自宅で~?
いったいどうやるの? 人工透析なんて!
もうホントに介護って大変!!
でもそのクリニックで2週間研修を受けさせてもらい、腹腔膜の人工透析に切り替える手術を受けさせてもらい
自宅で欠かさず毎日一日10時間の透析をすることになったのです。あー大変!
余談ですが、人工透析って本人はすごくツラいんですってね。透析後の体力の消耗はハンパないそうです。
自宅介護8か月後に、また軽い脳卒中を起こし、急きょ入院に。
医者から私だけにまた言われました。
「お気の毒ですが、もう治る見込みがありません。人工透析を続けながらでも命はあと1年持たないかもしれません。」
ガーーーン!! ウソでしょ?
あんなに元気に毎晩きげん良く働いていたのに、急に倒れて短い寿命を告げられるなんて!!
いや、何かキセキが起こって治るかもしれない。と自分の中で抵抗していました。
早くも一年後に回復の計画がダメになりそうです。
案の定、介護開始から8カ月が過ぎ
どんなに訪問看護やPTのリハビリをしても日に日に弱っていくのです。時々気を失い、その度に救急車を呼ぶ。
ホントに頑張ってる夫には申し訳ないけど、最期の時のことを予想してみたのです。
身内が亡くなることなど何十年もなかった、ましてや私は外国でひとりだ。
やっぱり考えてしまった。最期の時期を。。
夫の命が尽きるのは一年後だと。想定してしまいました。
なぜ終わりを決めないといけないのか?
病人が回復することも、亡くなってしまうことも
残酷だけど自分の中だけで想定しなくてはならない。
そう私に知らしめ決心させた出来事があったのです。
ある老老介護事件が私を変えた
自宅で介護を始めて半年後、たった半年だけど私は介護疲れがピークに達していました。(プッ!たった半年で)
これ、5年も10年も旦那さんや親御さんの介護を続けている人沢山いるんだよなー。みんなどうしてらっしゃるんだろう?
と思ってた矢先、ショックなニュースが飛び込んできた。Yahooジャパンニュース!!
72歳の女性が同居の76歳の夫と90歳代の義両親を殺害という事件。
その72歳の女性は自宅で一人で3人の寝たきり状態の老人の老老介護を15年間やり続け、疲労困憊の末ことに及んだそう。
行政にも施設入所の申請をしていたが順番待ちで、(あるいはその3人が家にいたいから!と拒否し続けたとか)とにかく奥さんも高齢なのに3人の高齢者をワンオペで介護しなくてはいけなかった。
おまけに生活費の為に週に3回外にパートに出ていた。なんと辛い状況か!
近所では、3人の年寄りを健気にまじめに15年以上も世話をしてるのに、いつも明るくてとても介護で悩んでるように見えなかったとの評判だったそうです。
それに比べ何と私はラクな状態で介護をしていることか。(自分に怒る)
同じ介護経験を持つ者として、その奥さんの心情がよくわかる。
たとえ逮捕されて人生にバツがついたとしても、この終わりのない介護苦役地獄からやっと解放される。
この病人3人からもこの生活からも自由になれる!と思ったに違いない。
が、いっとき介護から解放されても、また地獄が待っている。
刑務所内では厳しい序列があり先輩収監者グループ(牢名主)からの理不尽なイジメがあるらしい。
やはり弱い老人はイジメのターゲットになりやすいそうです。
なんと悲しい人生だろう。シャバで15年以上もまじめに正直に介護で苦労したあげく、塀の中でも理不尽なイジメにあうなど、この72歳の女性の人生はなんだったんだろう。
いったい彼女が何をしたというのだ。
この貴重な事件を教訓にしなければもったいない。72歳さんに申し訳ない!
「しょうがないから」と我慢し続けることなく、
とにかく「介護の終わり」を自分で決めてやろう!と心に誓ったのです。
時の流れに身をまかせてる場合ではないのだ。
私が介護生活を許容できるのはあと1年と決めた。
何がどうであれ
第一に1年後に回復してもらう。
第二に1年後回復しなかったら長期の介護施設に入ってもらう。
そして戦略的に計画していきました。明日は我が身ですもん。
介護の終わりを決める方法・考え方
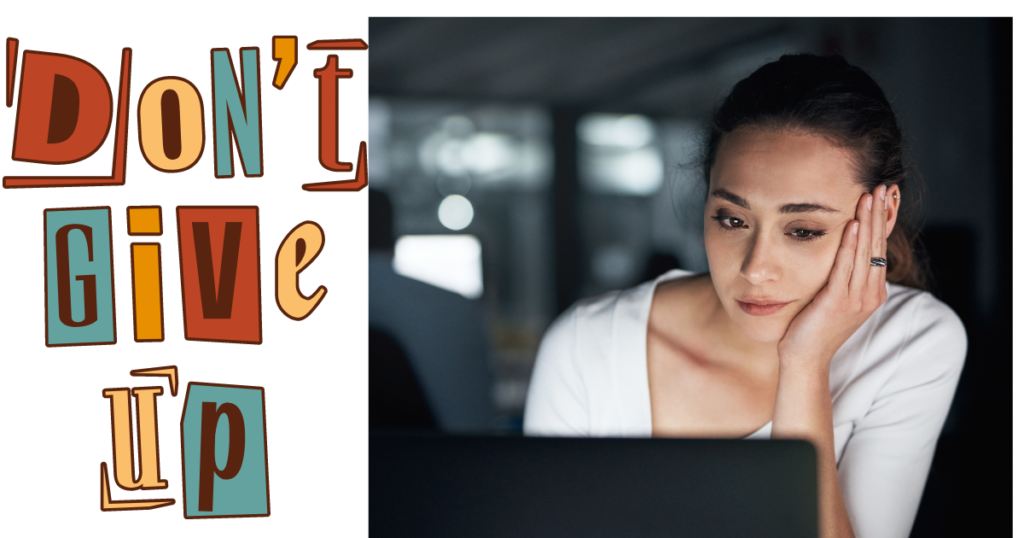
前述した、
①病人の回復する時期を決めてしまう
病人の回復する時期を決めてしまう。
え? おかしくない? そんなのわかるわけないじゃん!という声が聞こえますが、おっしゃるとおりです。
いつ完治するなんて医者でもピッタリ当てることはできません。
でも決めてしまうのです。だいたいお医者さんから病状や治る見込みや治る期間などを聞いていると思うので、それをもとに、暫定でもいいから「○年後の何月に治る」ということを決めてしまう。
この治る時期を決めておいて、やるべき来るべきイベントを逆算しておくんです。
仮に「1年後に治る」を設定したら、
「夫が今までかかっていた病院やリハビリ施設との契約解除、」
「治った後のリハビリ予定、」
「お互いの仕事復帰の時期、」
「復帰後から初めて貰える給料の時期と金額、」
などを1年後から落とし込んで逆算していく。
計画通りにいかなくていい、相手は病気なのだから。
ただ自分の中で今後の目安がつかめればいいだけです。
②長引く介護を終わる時期を決めてしまう
介護の終わる時期を決める。 ←これがすごく大事!
決めたからってタイホされるわけではありません💦
これは前述の事件の当事者72歳さんが私に教えてくれたこと。
永遠に続く介護を我慢を強いて継続した結果、悲しい結末にならないように、
自分から見切りをつける「勇気」を持つ。これ!
あとからいくらでも修正しちゃえばいい。たかが紙の上のプランなのだから。
ただただ自分でピリオドを打つと、踏ん切りをつける習慣がつく、イコール、暗闇から一筋の光をつかみやすくなる。
やはりこれも逆算と計画が必要です。
○年後に介護施設に入ってもらうと想定したなら、
「いつまでにケアマネさんに申請して、」
「どのタイプのしかも保険がきく施設に入るか、」(私達の場合、人工透析を毎日施術してくれる所)
「病人本人にも入所してもらうことを少しずつ理解をもらっておく」などです。
そしてそして加えたくないけど、
③生命の終わりを迎える時を想定する
生命の終わる時期を想定する。
なんて非道な!と思われることでしょう。
夫が亡くなってからわかったことですが、、もっと生前にこれを冷静にイメージしておくべきだったと思うのです。
なにも「早く天国に行ってくれ!」
と願うわけじゃなくて、
いずれ来るべく時に「備えよ!」
とあの時の自分に言いたい。
残された人はまだ現世で生活していかなくてはならない。後に立ち直って生きていくためのエネルギーを温存しておかなくては。。
具体的に言えば、
「生命保険の確認、」
「夫の銀行口座凍結になる前の処理、」
「残された車の売却、」
「最期を知らせる人達のリスト、」
「ホスピスケアに報告し保険を止めてもらう、」
「お葬式の段取り」
「夫の他界後の自身の生き方」など
残された遺族は介護が終わっても後始末がたくさん控えていたことを私はうっかり忘れていたのです。
相手の命が全うする時を想定するのは生きていく私の為に!なのです。
まとめ
結局私の夫は、会社帰りに翌日急病で突然の寝たきり状態➡私の2年間の在宅介護➡自宅で1週間のホスピスケア➡自宅で他界-66歳。
つまり最初の脳卒中発症から2年で亡くなりました。
【介護の終わりを戦略的に決める!】のまとめ
①病気から回復してくれる時期を決める
②介護の終了させる時期を決める
③生命の終わりを迎える時を決める
④介護の終結を決めることで老老介護の悲しい末路を防ぐ
⑤病人の回復する時期決定からイベントを逆算する-職場復帰など
⑥長引く介護を終わる時期決定する勇気を持つことで希望が見える
⑦生命の終わりを迎える時想定は遺族の生きる備えの為
今回の記事が全ての方に正しいとは思いませんが、はばかりながらもヒントになっていただけたらと思います。
クリックできるよ😽
またコメントもどうぞお気軽によろしくお願いします。
最後までおつきあい、ありがとうございました。
それでは、Good Luck✨✨
==================================
💟P. S. みなさんもキラキラをWEBで伝えてみましょ!💻☕📲☕
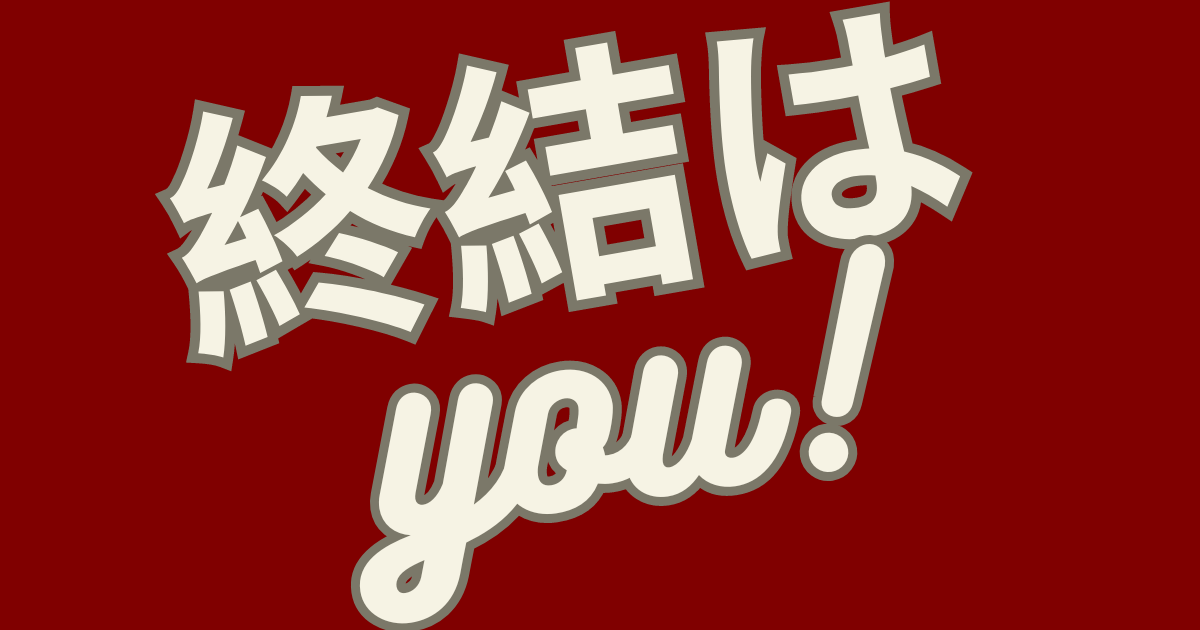
コメント